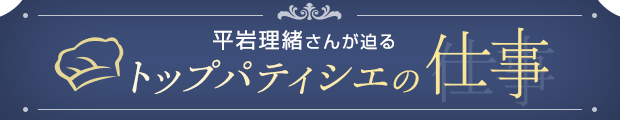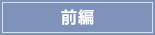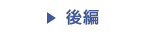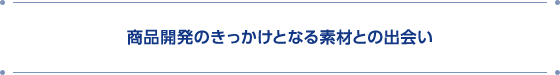菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、名古屋市「カフェタナカ」の田中千尋シェフです。お父様が自家焙煎珈琲店を創業したのは1963年のこと。コーヒーに合うお菓子をつくりたいとフランス菓子を学び、今や人気菓子店として複数の支店を持つまでに。2018年9月にも、新業態の店舗をオープンされました。常に活動し続ける田中シェフに、父子二代で育ててきたお店と商品づくりへの思いや、ますます女性の活躍が期待される製菓業界で今後やっていきたいことなど、お話を伺いました。
- 平岩
- こんにちは。今日は、2018年9月にオープンされた新店舗「カフェタナカ 稲沢文化の杜店」でお話を伺います。自動車販売の名古屋トヨペットさんと書店のTSUTAYAさんと一体となった面白い業態ですね。こちらでは、自家焙煎コーヒーと、それに合うアップルパイ、パティシエのつくる生食パンという3本柱で、本店をはじめとする他の店舗のお菓子に比べて、ラインアップをかなり絞り込んだ商品展開をされています。それについてはまた後程、より詳しくお伺いしますね。まずは、田中シェフが、お父様の珈琲専門店にパティシエとして参画されるようになった経緯をお聞かせください。
- 田中
- 子供の頃からコーヒーに慣れ親しんでいました。朝は父が淹れてくれたもの。午後も家で、食後にはお茶と、ティータイムを楽しむのが日常的だったんですね。当時、喫茶が何店舗かあって、私も、朝6時半に店に行き、7時にオープンするのを手伝っていましたが、毎日、同じお客様が同じ時間に、同じ店でコーヒーを召し上がるという、名古屋の喫茶文化の中で育ちました。その頃は、コーヒーとピーナッツなんかを一緒に出していたのですが、よりゆったり過ごしてほしいと、「コーヒーとスイーツという組み合わせがいいな」と考えるようになり、父のコーヒーに合うお菓子をつくりたいと思うようになりました。
- 平岩
- 名古屋のモーニングの喫茶文化は有名ですよね。田中シェフのお気持ち、お父様も嬉しかったことでしょうね。
- 田中
- フランスで製菓を学んで帰国し、24-25歳の頃に店に戻り、お菓子を出し始めました。最初は、フルーツのタルトとモンブランからスタート。6種くらいしか入らないショーケースに並べて、つくるのも一人でした。だから、この稲沢の店のアップルパイやタルト中心のラインアップは、自分にとって原点回帰とも言えるんです。でも、当時はタルトというのもまだ珍しい時代で、「タルトだけやっていても駄目だよ」と言われました。
- 平岩
- お客様には、徐々に受け入れられるようになっていったのですか?
- 田中
- うちの喫茶のお客様は、9割方が男性でした。男性の中には、スポンジのケーキは苦手、という方もいらっしゃるんですね。そんな方がタルトを召し上がって下さるところから始まり、次第に、ご家族と来てくださるようになりました。それでも、初めは1日に100個つくるくらいでしたね。
- 平岩
- 今は店舗もスタッフの方の人数も増えて、作られるお菓子の量も、大幅に増えましたね。いくつかの転機がおありだったかと思いますが・・。
- 田中
- やはり、JR名古屋タカシマヤへの出店が大きなきっかけでした。2000年のタカシマヤ開業時すぐではなくて、オープンから3年くらいしてからでしょうか。私が店に戻ってきて5年くらい経っていました。最初は催事出店からで、その後、常設店を出すことに。その後、三重県のジャズドリーム長島の出店は11年目くらいでしたね。実は何度もお断りしたのですが、ご担当の方の熱意に押されて。こういうのって、信頼関係と人と人との繋がりなんですよね。
- 平岩
- 百貨店でお菓子を販売されたことが、大きな変化に繋がったのですね。
- 田中
- それはもう、一個人店がいきなり周りは大手ブランドばかりの環境に飛び込んだようなものですから、さまざまな勉強しないといけなかった。試行錯誤の日々でしたが、やってみて、結果的に成長できたのかなというのはありますね。
- 平岩
- 私も、タカシマヤの店舗で出会った「名古屋フィナンシェ」が印象的でした。地元の西尾抹茶と八丁味噌を使ったフィナンシェは、名古屋土産としてもわかりやすいですよね。
- 田中
- 名前も大事なんですよね。でも「名古屋フィナンシェ」って、商標登録できなかったんですよ。
- 平岩
- そうだったのですか?なかなか難しいのですね・・。昨今、商標登録は、お菓子屋さんにとっても重要な問題ですね。
- 田中
- ずっと作ってきたモンブランは、メレンゲの土台がしけるので、最初は、持ち歩き3時間以内としていました。でも、百貨店の店舗は、2018年の春から生菓子をやめたんです。クッキー缶が売れるようになって、やめさせてもらえたという感じですね。やっと、焼き菓子を認めてもらえたな、と思いました。
- 平岩
- 缶入りのクッキー「レガル・ド・チヒロ」は、お取り寄せスイーツとしても大人気で、全国から注文があり、限定数でなかなか手に入らないと評判ですね。
- 田中
- 雑誌『婦人画報』のオンラインショップでブレイクしましたね。缶も手作りのものがいいと。あれは、色ムラやゆがみもあるデザインで、500ロットずつくらいしか作れないんです。「おもてなしの心」を表現したいと、「カフェタナカ」の創業当初のロゴをデザインに採り入れた、レトロな雰囲気にしています。
- 平岩
- あのレトロ感が、逆にモダンに感じられて、新鮮な魅力なんですよね。時々、色の違う缶も出て、これがまた可愛らしいと、ファンの心をくすぐっています。
- 田中
- 芸術的、というより、もっと素直に直感で、可愛いとか、美味しそうとか思えるものがいいと思うんですね。
- 平岩
- そうそう、先ほど、こちらの厨房内をガラス越しに覗いたのですが、壁の一部に、素敵な模様入りのタイルを使用されていますね。そういうことも、女性ならではの感性かもしれない、と思いました。
- 田中
- 厨房の中にも、やさしい、ナチュラルな雰囲気を採り入れたかったんです。その厨房から、素材を活かしたものづくりをするのですから・・。季節ごとのフルーツの魅力や、フランスで初めに食べて感動したモンブランの味や、パリのマルシェで感動した素材達のように、直球で味わえる美味しさを伝えていきたいです。そして、コーヒーとスイーツとのマリアージュを、自分で組み合わせて提案していきたい。いつまでも変わらず、美味しいティータイムを過ごしてもらえるということを目指したいですね。
- 平岩
- 田中シェフの原点は、やはりお父様の珈琲店におありなのですね。それが、今の田中シェフならではのお菓子づくりに繋がっていらっしゃるというのがよくわかります。







- 平岩
- このお店も、実際に訪問された農家さんから届くりんごを使ったアップルパイを看板メニューにされていますが、ここ数年は、果物をはじめ、カカオ農園に至るまで、産地をよく見にいかれていますね。
- 田中
- 最初のきっかけは、実は東京・尾山台「オーボンヴュータン」の河田勝彦シェフから、長野の生産者さんをご紹介いただいたことでした。それから、塩尻や安曇野などの農園に行くようになっていき、今では青森から沖縄まで様々な生産者さんのもとに足を運んでいます。また、カカオやバニラなどの産地へも10年ほど前から興味を持って行くようになりました。
- 平岩
- 私も同じ頃、10年くらい前から、パティシエの皆様が使われる素材のフルーツに興味を持って、農家さんを訪問するようになりました。
- 田中
- 素材について、問屋さんの先の情報がなくて、勉強したいと思っていたんですね。このりんごや洋梨も、そのままでももちろん美味しいけれど、より魅力を引き出すにはどうしたらいいのか?と。スタッフにも「素材を大切にしよう」と言っていますが、私達の仕事は、生き物から“分けてもらう”ことで、それを生まれ変わらせるという素敵で責任のある作業なんですよね。そう思って真剣に取り組むべきです。お菓子屋さんになりたいという子供達にも、食べる人達にも知っていてほしい。
- 平岩
- 仰るとおりですね。私の周囲でも、素材を知れば知るほど、生産者の方への敬意をもって、その持ち味をどう活かそうかという気持ちになる、というパティシエの方が増えています。
- 田中
- 素材について学ぶことで、見えてくるものがあります。そうすると、難しいことを考えずに笑顔になってもらえる、記憶に残る味というのがいいと思う。結果、シンプルに戻っていくんです。
- 平岩
- わかります。この新店には、そういう田中シェフの思いが強く反映されていますね。
- 田中
- お菓子をシンプルにしたから楽になるという訳ではないんですよね。学びと、ものづくりという答えのない闘いをつきつめることで、新しいアイデアや楽しみが生まれてくるものなんです。
- 平岩
- 田中シェフは、どのような農家さんとの出会いによって、お菓子を作りたいと思われるのでしょうか?
- 田中
- ものづくりへの考え方が一致するか、お菓子づくりへの理解がある農家さんですね。自分が現地に行って、味わって理解することで、このフルーツでこんなお菓子を作ってみたいと思う。でも、例えば、ある青森の農家さんは、りんごを使ったお菓子をご覧になって、「りんごを殺している」と仰るんですね。そういうことも学びになります。私も、10年前は、フランスで学んだことが一番、と思っていました。でも、食文化なので変化していくのは当然のことです。今は社会が高齢化もしています。だから、今の時代に合ったお菓子、おやつをつくっていかなくてはと思います。
- 平岩
- 先ほど、クッキー缶「レガル・ド・チヒロ」のお話も出ましたが、焼き菓子に使う小麦粉は、どのように選んでいらっしゃいますか?
- 田中
- クッキー缶には「エクリチュール」を使っています。ちょっと価格が上がりますが、パイには「テロワール ピュール」を。他にも国産の「ゆめちから」といった小麦粉も含めて、粉の素材の味を感じられるものを選んでいます。バターや他の材料も受け止めて、表現できる味を持ったもの。やっぱり、その粉でないとその味が出ないんですね。粉によって全然違ってくるので、奥が深いなと思います。



※店舗情報及び商品価格は取材時点(2018年11月)のものです。
最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。